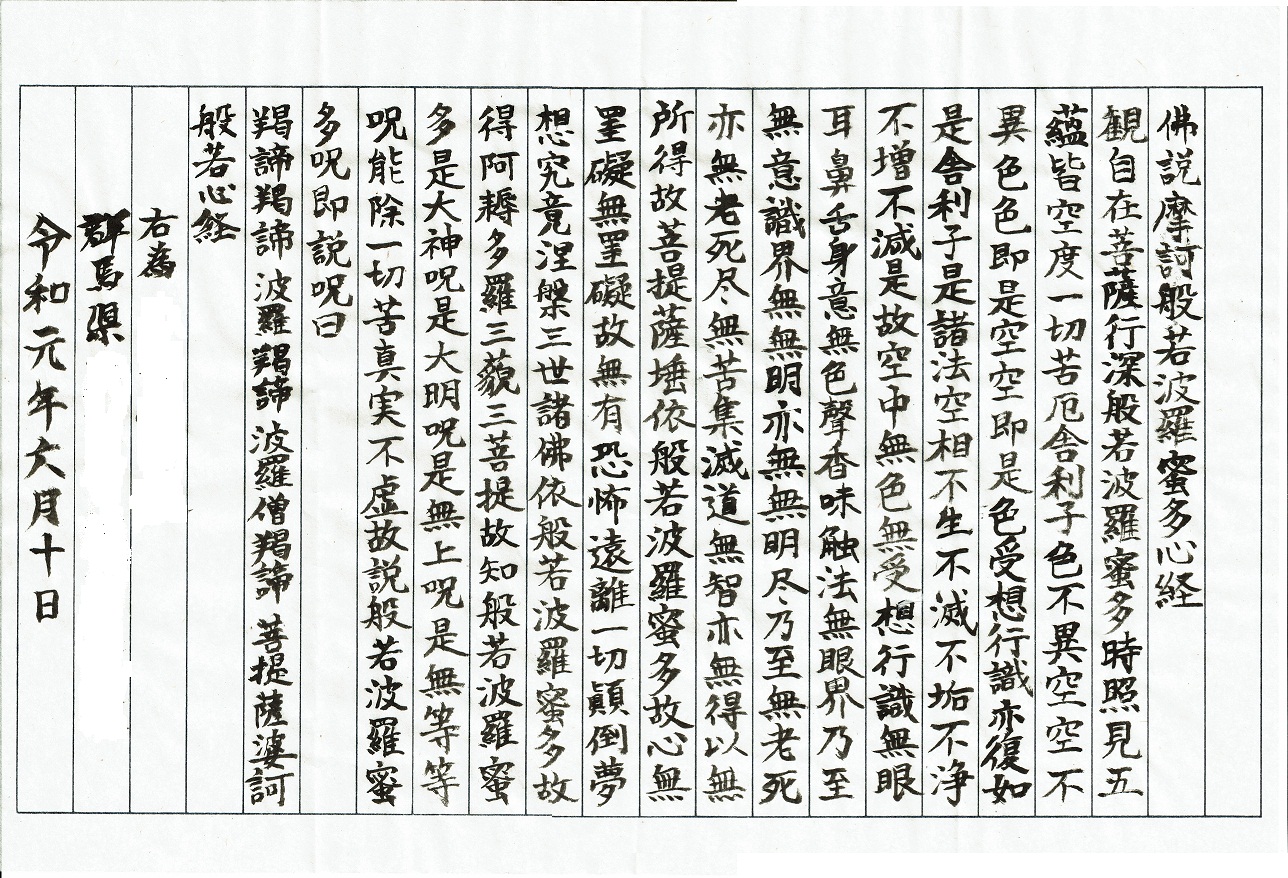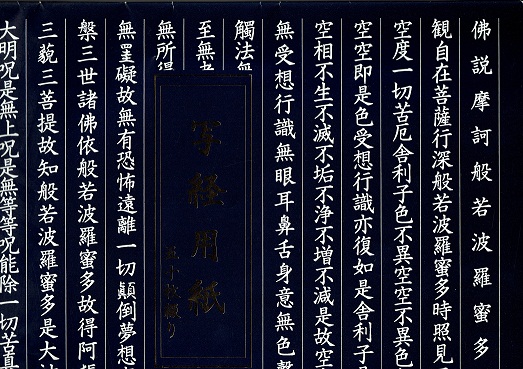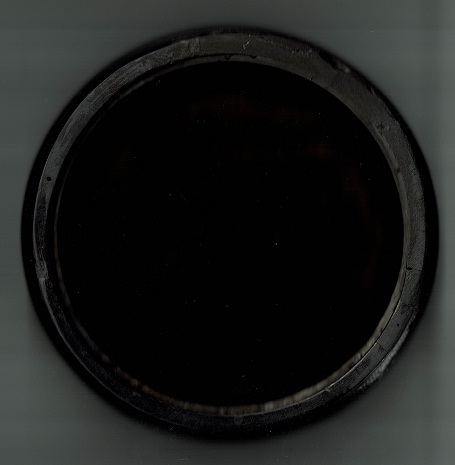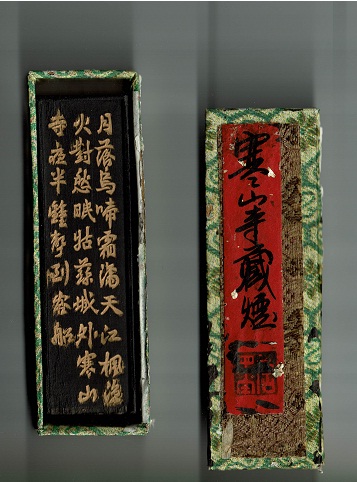TOP 自分の思い 邪馬台国 バイク 瓢箪 霊場巡り 囲碁と将棋 CAD/CAM 生産管理 海外の思い出 索引
写経その後
その後、ほぼ毎日般若心経を写経している
なぜか、例えば坂東33ヶ所全てに写経した般若心経を納めようとすると
一枚を一ヶ所のお寺に納めるとすると特別霊場も含め35枚の写経が
必要になる
一日に書けるのはせいぜい一枚なので、約40日かかる事になる
関東88霊場巡りを同時にやろうとすると更に100枚必要になり、3ケ月
後でないと開始できない計算になる
霊場巡りから帰ってくれば、写真等をHPに掲載するのに一日に1ヶ所が
せいぜいである、一日で5ヶ所回ってきたとすると、記憶が薄れないうち
にほぼ毎日HPを作る事になる
つまり、霊場巡りを始めたらもう般若心経を書いている暇は無いのである
さりげなく納経したいと思ったが、いざ始めて見ると、半年般若心経を書
き続けて、100枚以上貯めて、半年かけて書いたものを各お寺に納める
ことの繰り返しになる
一年の内半分は行きたくてもお寺巡りはできない
毎日書けば半年で200枚書けるではないかというかもしれない
実際やってみると、酒を飲んでしまったり、夜蒸し暑くてそれどころではな
かったり、毎日は出来ないのである
四国108ヶ所(88ヶ所+別格霊場20ヶ所)に春に行こうと思ったら、思い
つくのが1月では遅いのである
結局春と秋の2回に分けたのもそれが理由だった
5月の時点では実際は100枚以上溜まっていたのだが、いざいってみると
他の札所と違い、本堂と太子堂の2ヶ所に納経するならわしの様だった
つまり108X2=216枚必要だったのである
また納め札を現地の一番札所で購入したのだが、200枚で100円と値段
は安いのだが、住所、氏名、納めた日、願い事を書くようになっている
別格霊場は表紙が違うので別に購入するこれは別格1番でないと売ってい
ない
一日に10ヶ所位廻りたいのだが出来ないのである
どうしても一ヶ所に30分位滞在する事になってしまう
また、前の日に納め札をホテルで30分くらいかけて筆ペンで書くのだが机も
ないような薄暗い中で書くのは結構つらい
食事の時にビールを飲んでしまい、風呂に入ると尚更つらい
これも春に全部回れなかった理由である
そんなにあせらずに一ヶ所のお寺に1時間ぐらいいる気になればいいのだが
精神修業が足りない未熟者にはそれができない
一通り写真を撮り、線香とろうそくを本堂、太子堂各々であげ、般若心経を
2回唱え、最後にご朱印を貰う
全部きちんとやると、お寺をじっくり見ていることが出来なくなってくる
悲しい性である
四国の後もう一年近く新しい札所巡りをしていない、般若心経はいつの間にか
200枚を超えた
またやろうかなと思っている
<般若心経のサンプル>
写経用紙にもいろいろあり、若干最後の方の書き順や内容が違っているが
右為として、願い事を書くのと、日付、氏名は皆書くようである
住所や最後に謹書等と書くものもある
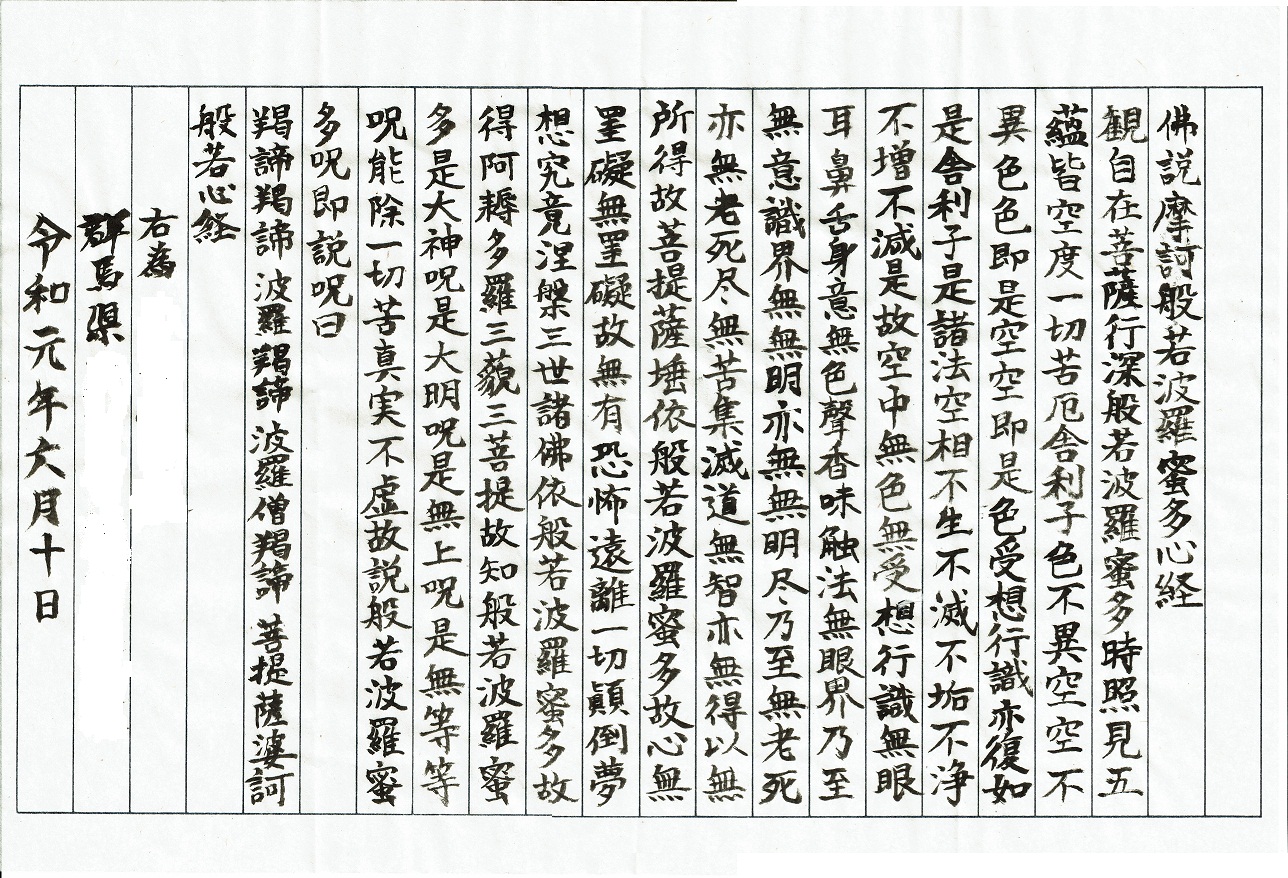
<写経用紙の表紙>
これは今までに購入した中で最も安いもので、50枚つづりで800円である
100円ショップでは7枚100円なので、それよりも安い
秩父札所18番の国道140号線沿いのお寺で売っている
1番札所では同じものを1000円で売っており、18番が一番安い
四国88か所でも同じ銘柄のものを見たが、これよりも横幅が5cm位広く、
そのかわり1200円した
文房具店では20枚つづりで1000円位が相場である
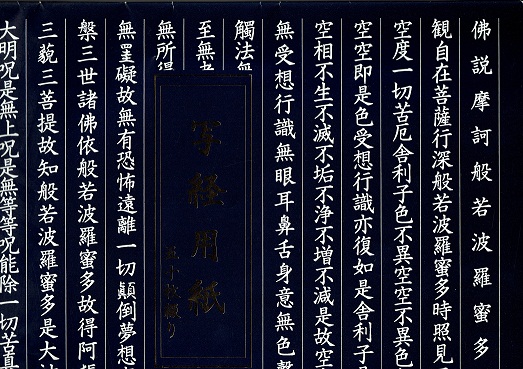
<愛用の硯>龍の彫り物のあるので恐らく中国製か香港製と思われる
端が掛けてしまっているが、丸くて墨をすりやすいし、海(墨をためておくところ)
がやや広く使いやすい、もっと大きい硯でも海が小さかったり、擦る場所が
狭かったりするものがある
ふた以外には余計な飾りが無いのが私には丁度良い
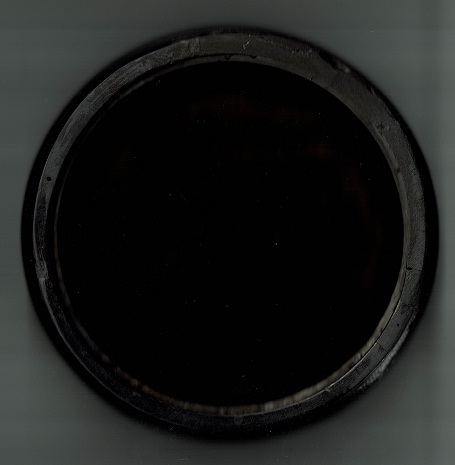

川越の書道店で購入
<文鎮>文鎮も龍の掘りものにした、高崎の書道店で購入

<中国製の筆>先には竹のふたがついている、
280円だったが、300円のものもある、何の変哲もないのだが、日本製より
書きやすい

<古物商で購入した墨>
上段が現在使っている墨、この位の大きさが硯とあっていて使い易い
現在4本目である、ほぼ1年で1本使う、丁寧に使えば2〜3年持つのだが
比較的安いので(古物商で500円位)、持ちづらくなったら構わず捨てて
取り換えている
下段の墨は全て古物商で集めたもの、骨董品なので飾りとして持って
いるのが本来の姿らしいが、値段が500円〜2000円位で文房具店で
新品を買うより安く、しかも使っていて気分が良い
一番大きな景雲飛と書いてあるものは、硯を大きなものに取り換えて使って
みたが、濃い墨を早く磨る事が出来る
接地面積が大きいためと思われる(10mmX45mmX150mm)
中央の墨に松煙という文字が見られるが、松を燃やしたススを膠(にかわ)
で固めたもので、中国製の特徴である
日本製は菜種油や機械油等を使用するらしい
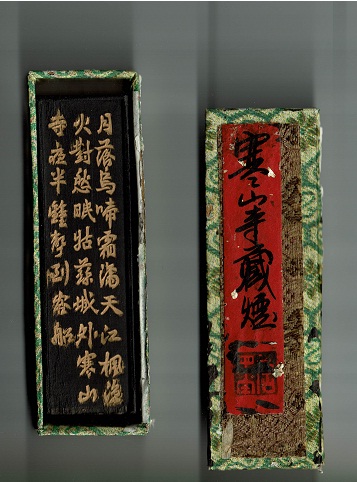

TOP